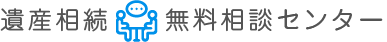日本は現在超高齢化社会となっており、まさにこの先は大相続時代となっていきます。
この社会に対応していくため、民法で定められた相続に関する法律(相続法)が約40年ぶりに改正され、その多くは令和1年7月1日から施行されています。
相続法の改正によって今までの扱いが見直されたものや新設された制度について解説していきます。
相続法改正の概要
ではまず改正された相続法の全体像を把握していきましょう。
改正された分野は次の6つです。
①配偶者の居住権を保護するための方策
⇒配偶者居住権・配偶者短期居住権の新設
(配偶者を失った相続人が引き続き現在の家に住むことができる権利。)
②遺産分割等に関する見直し
⇒預貯金の仮払い制度の新設、特別受益の持戻し免除の意思表示の推定
(凍結された被相続人の預金口座から、家庭裁判所の判断を得ることなく一定額の預金の引き出しができるなどといった制度、生前受けていた贈与を相続財産に加えること(=持ち戻し)の免除)
③遺言制度に関する見直し
⇒自筆証書遺言書に添付する財産目録がパソコンで作成可能になる、自筆証書遺言書が法務局で保管してもらえるようになる
(今までは自筆証書遺言書は全て自筆でなければならず、保管も自分で行わなければならなかった)
④遺留分制度に関する見直し
⇒遺留分減殺請求の効力は金銭支払いが原則とされる、遺留分の算定方法が明確になるなど。
(これまでは現物返還が原則だったため、遺贈などによって受け取った不動産がある場合にトラブルになりやすかった。また、特別受益に当たる贈与の算定は無期限だったが期限が設けられることになった。)
⑤相続の効力等に関する見直し
⇒「遺言させる」旨の記載の遺言書があった場合これまでは法定相続分を超える不動産の相続をした場合に登記をしなくても第三者に対抗することができたが、相続法改正後は登記が無ければ対抗することができなくなるなど。
⑥相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
⇒法定相続人以外の者も貢献度に応じて金銭の支払いを要求できることになった。
(例えばずっと被相続人の介護をしていた長男の妻など、法定相続人でない者はこれまで遺産をもらうことができなかった)
ざっとまとめるとこれらが主な改正の全体像となります。
ここからは中身を詳しくみていきましょう。
相続法改正による8つのポイント
では先ほど挙げた全体像の中でもポイントとなる8つの項目について詳細に解説します。
配偶者居住権の保護
この度の相続法改正の目玉ともいえる項目で、2020年4月から施行されます。
配偶者居住権をお話しする前に「法定相続分」について知っておく必要があります。
法定相続分とは民法で定められた遺産の取り分のことです。よくあるパターンとしては配偶者1/2、子供が残りの1/2を等分するというものです。
例えば父が亡くなって、相続人が母と息子1人だった場合、法定相続分は母1/2、息子1/2となります(息子が2人いればそれぞれ1/4ずつ相続することになります)。
そのため遺産が自宅不動産3,000万円分、現金3,000万円分あった場合、自宅不動産については分けることができず、手放してしまったら住むところが無くなってしまうという点から母が自宅不動産を、息子が現金を相続するケースが多いのです。
しかし、そうなった場合母は自宅不動産が手に入る代わりに現金を手に入れることができなくなってしまいます。
つまりは父が亡くなった後の生活が苦しくなってしまう可能性があるのです。
逆に現金だけ相続したとしても、住居が無ければ家を借りることになりますので家賃が発生します。例のように高額の現金があればよいのですが、少なかった場合も生活が苦しくなる可能性があるのです。
また、遺産の額によっては自宅不動産を手放さざるを得なくなる可能性もあります。例えば自宅不動産が3,000万円、預貯金が2,000万円しかない場合などです。この場合に法定相続分通り遺産分割をしようとしたら、自宅不動産を売却してお金に変えて2,500万円ずつ相続することになるからです。
このように、配偶者が居住の権利を保護されないことは以前から問題視されていました。
そこでこの度の相続法改正によって「配偶者居住権」が新設されることになったのです。
●配偶者居住権
配偶者居住権とは、相続が開始する前から配偶者が一緒に住んでいた被相続人の自宅不動産に、終身まで住み続けることができる権利のことを言います(期間は任意で設定できます)。
この建物について所有権の相続をしなかったとしても、住み続けることができます。
少しイメージしにくいと思うのですが、不動産には「所有権」があります。
自宅不動産を第三者に売却すれば第三者に所有権が移ります。相続の場合は遺産分割協議を行って、自宅不動産を相続することになった相続人に所有権が移ります。
所有権を持っている人が不動産を自由に使用したり、処分をしたりすることができますので、これまでは例えば子供が不動産を相続した場合、配偶者が今まで住んでいた自宅に住みたくても住めなくなるというケースも少なくありませんでした。
配偶者居住権が認められたことによって、所有権を①自由に使用する権利と②その他の権利(収益・処分など)に分けることができるようになったのです。
これによって配偶者には①自由に使用する権利を、子供には②その他の権利を相続させることができるようになりました。
例えば遺産が不動産3,000万円分、現金3,000万円分だった場合、母が自宅不動産を配偶者居住権で1,500万円と現金1,500万円、息子が自宅不動産をその他の権利(「負担付所有権」と言います)で1,500万円と現金1,500万円を相続するといった形です。(配偶者居住権の価値は不動産の現在価値-負担付所有権の価値で決まります。)
こうすることによって母は不動産に住むことができるのと同時に現金を手に入れることができるようになります。
<配偶者居住権を認められるためには>
配偶者居住権は
・被相続人の遺言
または
・遺産分割協議
によって、配偶者に取得させることができます。
配偶者居住権を認めてもらうためには、次の2点を満たす必要があります。
・相続開始の時点で、被相続人が所有していた自宅に住んでいた配偶者であること
・配偶者居住権の登記をすること
(登記をしなかった場合、所有者が売却してしまっても対抗することができなくなります。)
●配偶者短期居住権
こちらは被相続人の死亡から遺産分割協議の間の一定期間、配偶者に認められた居住権のことです。
もし配偶者居住権が認められなかったとしても、
・遺産分割によって自宅不動産の帰属先(誰が取得するか)が確定した日
・相続開始から6ヶ月を経過した日
のいずれかの遅い日まで、自宅不動産を使用することができる権利です。
ただし、配偶者が「無償で暮らしていた自宅不動産」であることが条件となります。
先ほどの例で考えると、母が3,000万円の現金を、息子が3,000万円の自宅不動産を相続することになった場合、被相続人の死亡日が3月1日だった場合、早くても6ヶ月後の9月1日までは配偶者短期居住権によって自宅不動産に住むことができます。
遺産分割協議が整った日が12月1日だとしたら、その日まで自宅不動産に住むことができます。
仮に自宅不動産を被相続人が第三者に遺贈(遺言書によって贈与を行うこと)した場合や配偶者が相続放棄(一切の相続をしないこと)を行ったとしても、一定期間(この場合は新たな所有者から「配偶者短期居住権の消滅請求」がなされますので、この請求を受け取ってから6ヶ月間)は無償で使用できるということになります。
預貯金の仮払い制度
次は預貯金の仮払い制度です。こちらは2019年7月1日から施行されています。
預貯金の口座は、名義人が亡くなったら凍結されて引き出すことができなくなります。
そのため被相続人が名義人である口座に預金をしていた場合やそこから生活費の引き出しをしていた場合は亡くなった後に生活費や葬儀費用・病院代が引き出せなくなって困ってしまうというケースがありました。
これまでは預貯金を引き出すには
・相続人全員の合意
・遺産分割協議を行い口座の凍結を解除
のいずれかの方法によって行うしかありませんでした。
速やかに遺産分割協議を行い口座の凍結を解除できればよいのですが、遺産分割協議はお金に関する事ですのでトラブルになるケースも多く、長く協議が整わない場合は数年にわたって遺産分割協議を行うこともあります。
この問題を解決するために、今回の改正で新設されたのが「預貯金の仮払い制度」です。
預貯金の仮払い制度によって、遺産分割協議の成立前であっても相続人全員の合意がなくても一定額の預貯金の引き出しができることになりました。
次の方法で仮払いを受けることができます
①金融機関で請求する
遺産である預貯金の一定額までについては、家庭裁判所での手続きを経ることなく引き出すことができる
ようになりました。
ただしこの仮払い方法には上限があり、原則は次の計算式で計算された金額となります。
相続開始時の預貯金債権の額(口座基準)×1/3×当該払い戻しを行う共同相続人の法定相続分
※一金融機関の上限は150万円までです。
例えば預貯金の額が1,500万円で、法定相続人が配偶者と子供1人の家庭で配偶者が預貯金を金融機関で仮払い請求した場合は
1,500万円×1/3×1/2=250万円
となりますが、上限は150万円ですのでこの場合配偶者が引き出せるのは最大150万円ということになります。
さて、ここで気になるのが葬儀費用ですが、2017年に行われた日本消費者協会のアンケートの結果によると、葬儀費用の平均は196万円だそうです。
預貯金がもう一つ別の金融機関にあればもう少し引き出すことが可能ですが、高額の預金をいくつもの口座にある人は少ないのではないでしょうか。
また、2016年に厚生労働省が行った調査によると貯蓄総額の平均は約1,033万円だそうです。
これでは葬儀費用すら出すのが精いっぱいになってしまう可能性があります。
そんな時は次の方法で仮払いを受けることができます。
②家庭裁判所に仮払いの申し立てをする
こちらは家庭裁判所に仮払いの申し立てをすることによって、預貯金の引き出しを行うことができる制度です。「仮払いの保全処分」と言います。
保全処分には上限が無く、仮払いの必要性が認められた場合は他の共同相続人の利益を害しない限り仮払いを受けることができます。
高額の引き出しができることがメリットですが、家庭裁判所に申し立てをする必要がありますので複雑な手続きを踏まなければならず、費用も発生します。
銀行口座からの引き出しだけではどうしようもない場合に申し立てをすることになりそうですが、裁判所に申し立てることは簡単ではありません。この場合は弁護士などの専門家に依頼をしたほうが良いでしょう。
特別受益の持戻し免除の意思表示の推定
まず聞いたことのない言葉がたくさん並んでいますので、この言葉の説明からしていきたいと思います。
●特別受益
特別受益とは、相続人が被相続人から生前に受けた贈与(生前贈与)や、相続開始後に受けた遺贈(遺言によって財産を譲ること)など、被相続人から特別に受けた利益のことを言います。
生前贈与については民法第903条1項によって次のものが対象となっています。
・婚姻のために受けた贈与
・養子縁組のために受けた贈与
・生計の資本として受けた贈与
例えば結婚する際に受け取った支度金や、マイホームを取得する際に受け取った資金、開業のために受け取った資金などは生前贈与のうち特別受益に当たります(生前贈与のうち結婚式の挙式費用や大学の学費などは特別受益には当たらないとされています)。
遺贈については特に定めがありませんので、遺贈によって受け取った財産は全て特別受益となります。
なぜ特別受益という制度があるのかというと、極端な話になりますが相続人が2人いて、一方の相続人に多くの財産を生前贈与されていた場合に遺産相続で法定相続分通りに遺産相続をしたらもう一方の相続人は少ない金額の遺産しか受け取れなかったという結果になってしまうからです。
例えば相続人が姉妹2人で、姉が結婚する際に支度金として500万円受け取っていたが自分はまだ結婚しておらず支度金をもらっていない。その状態で被相続人である父が亡くなり遺産が1,000万円あった場合に法定相続分で相続をすると、姉500万円、妹500万円の相続をすることになります。
結果として、姉は父から1,000万円を、妹は500万円を相続したことになるのです。
こうなると妹は不公平な相続をされたことになります。
このような結果になることを防ぐために特別受益の制度があります。
この特別受益の額を反映してそれぞれの相続人の相続分を計算することを「特別受益の持ち戻し計算」と言います。
●特別受益の持ち戻し計算
特別受益の持ち戻し計算についてですが、これまでは次の計算式で行われていました。
{相続開始時の財産(遺贈を含む)+特別受益}×法定相続分―特別受益=具体的相続分
=みなし相続財産 (又は指定した相続の割合)
具体例を挙げていきます。
相続人…配偶者 特別受益2,000万円
子供(兄) 特別受益1,000万円
子供(弟) 遺贈1,000万円
相続開始時の遺産額…5,000万円
特別受益を計算せず遺産額を5,000万円とした場合、それを法定相続分で配分したら
配偶者…5,000万円×1/2=2,500万円
兄…5,000万円×1/4=1,250万円
弟…5,000万円×1/4=1,250万円
が相続額となります。
特別受益を計算した場合、みなし相続財産は5,000万円+2,000万円+1,000万円=8,000万円で、それを法定相続分で相続するとしたら
配偶者…8,000万円×1/2=4,000万円
兄…8,000万円×1/4=2,000万円
弟…8,000万円×1/4=2,000万円
が、それぞれの相続額となります。
そこから特別受益額をマイナスしていきます。
配偶者…4,000万円-2,000万円=2,000万円
兄…2,000万円-1,000万円=1,000万円
弟…2,000万円+1,000万円(遺贈)-1,000万円=2,000万円
こうすることによって、特別受益を受けた人と受けていない人でもらえる遺産額に不公平が無いようになる仕組みなのです。例では弟が特別受益を計算せずに受け取る額と、特別受益を計算して受け取る額では750万円もの差が出ることになります。
●持戻し免除の意思表示
では特別受益がわかったところで最後に「持ち戻し免除の意思表示」についてです。
持ち戻し免除の意思表示は民法第903条3項に定められている規定で、被相続人が遺言などによって「特別受益の持ち戻し計算をしなくてもよい」などと意思表示をしている場合はその効力を認めるというものです。
この意思表示があれば、遺産分割をする際に特別受益の持ち戻し計算をする必要がなくなります。
(法定相続人全員が持ち戻し計算をしなくても良いと合意をしている場合も特別受益の持ち戻し計算をする必要はありません。)
さて、この持ち戻し免除の意思表示についてですが、ここまで読んでいて「元々あったシステムでは…?」と思われたかと思いますが、そうなのです。元々あったシステムなのです。
しかし、持ち戻し免除の意思表示について知っている方が少なかったために活用されるケースは稀でした。
では何故今更見直されたのかというと、活用しないことによって配偶者が相続できる遺産額が少なくなってしまうからなのです。
よくあるケースとしては、被相続人が生前に自宅不動産を贈与していた場合など、高額の生前贈与が行われていたなどが挙げられます。また、知っていたとしても相続人全員が合意をしなければこの制度を利用することはできません。
自宅不動産を受け取っていたので住居はあるものの、お金が無い…というわけです。
そこで今回の法改正によって、これまで持ち戻し免除の意思表示を認める3項までだった民法第903条に4項を追加し、一定の要件を満たしていれば持ち戻し免除の意思表示があったと推定されることになりました。
一定の要件は次のとおりで、すべての要件を満たす必要があります。
①婚姻期間が20年以上の夫婦
②居住の用に供する建物又はその敷地について贈与(遺贈)
この2つの条件を満たす贈与または遺贈だった場合には、遺言がなくても相続人全員の合意が無くても持ち戻し免除の意思表示があったと推定される、つまり配偶者が多く遺産を相続することができる=保護されるというわけです。
少し長くなりましたが、これが見直された「特別受益の持戻し免除の意思表示の推定」です。
こちらも配偶者居住権と同じく配偶者を保護するための法改正ですね。
自筆証書遺言の方式の緩和
自筆証書遺言書は紙とペンがあれば自分のタイミングで作成できるし費用もかからないので最も選ばれる遺言の方法です。
しかし自筆証書遺言書の内容がその通りに実行されたケースはわずか3%ほどなのだそうです。
その理由として、自筆で書けば何でもいいわけではなくきちんと法律に則って自分の字で全ての内容を書かなければならないのですが、法律に則って書かれた遺言書ではなかったり、すべてパソコンで作ってしまった遺言書だったり…ということが挙げられます。
他にも大切にしまってあったため発見されなかった場合や相続人などの手によって改ざんされてしまった場合、文字の判別ができない場合など、実に様々なケースで無効になってしまいます。そのため、わずかな確率でしか内容通りに実行することができないのです。
これがこの度の法改正によって次の点が変更になりました。
・財産目録については自筆でなくても良くなった。
・法務局で遺言書を保管することができるようになった。
●財産目録については自筆でなくても良くなった
遺言書自体は変わらず自筆で作成しなければなりません。
しかし、財産目録(財産の詳細)については制度が緩和されたため、自筆ではなくパソコンで作成することが可能になりました。
不動産をお持ちの方は詳細に書かなければならなかった不動産の情報や、預金口座などについて自筆で書く必要が無くなったのです。例えば山などの不動産をお持ちの方は、複数の地番(一筆の土地ごとにふられた番号のことで、土地にはすべて地番がふられています)をお持ちの方が多いのではないかと思います(経験上山にはかなりの数の地番がふられています)。
財産目録には持っている土地の所在、地目、面積などをすべての土地分記載しなければなりません。考えただけで嫌気がさす作業です。これが自書でなくてよくなったのです。
ただし、財産目録をパソコンで作成したものには全てのページに署名捺印をする必要があります。
財産目録の代わりに不動産がある場合は登記事項証明書を、預金がある場合は通帳口座のコピーを添付することも可能です(登記事項証明書や口座のコピーにも署名捺印は必要です)。
この自筆証書遺言書の方式の緩和は2019年1月13日から施行されています。
●法務局で遺言書を保管することができるようになった
これまでは自筆証書遺言書は自分で保管しなければなりませんでした。
そのため亡くなった後に見つけられないこともあれば、生前に失くしてしまうことや災害により無くなってしまうこともあります。また、無くなっていなくても相続人によって隠されたり改ざんをされてしまうというリスクもありました。
今回の法改正によって、自筆証書遺言書を法務局で保管してもらうことができるようになりました。
これは非常に大きなメリットだと言えます。
具体的にメリットを挙げると次のようなものがあります。
・紛失、盗難を防ぐことができる
・改ざんを防ぐことができる
・検認が不要になる
・不備が無くなる
検認とは家庭裁判所に遺言書の存在や内容を認めてもらうことです。検認を行うことによって改ざんなどを防止する目的があります。
自筆証書遺言書が見つかった場合は開封せず、速やかに家庭裁判所で検認を受ける必要があります(検認をせずに開封した場合は5万円の過料が科せられます)。検認をしてもらうためには家庭裁判所に申し立てをしなければならないため、手間がかかりますし費用もかかります。
しかし、法務局で保管をしてもらう場合は改ざんの心配が無いため検認をしてもらう必要がありません。
また、保管に必要な範囲で中身のチェックをしてもらえるため不備が無くなります。そのため遺言書が無効になってしまう可能性も低くなるのです。
法務局での保管の制度は2020年7月10日から施行されます。
開始後、自筆証書遺言書は法務局で保管してもらったほうが良いでしょう。
保管の申請は、遺言者が自ら法務大臣の指定する法務局(遺言保管所)にて行います。申請をする際には遺言者が自分で作成したもので間違いが無いか確認するため本人確認も行われます。
申請後は遺言保管所にて原本を保管すると同時にデータ化されるため、遺言者はいつでも閲覧請求をすることができます(遺言者が生きている間は遺言者以外が閲覧することはできません)。データ化するため紛失するリスクがなくなります。
また手続きをすれば内容の変更をすることもできます。
遺言者が亡くなった後、相続人や受遺者(遺言によって遺産を受け取ることができる人)は遺言保管所に「遺言書保管事実証明書」(遺言書が遺言保管所に保管されているかどうかを証明する書面)や「遺言情報証明書」(遺言書の画像情報などの証明書)の交付請求を行うことができます。また、遺言書の閲覧も可能です。
相続人などが遺言書に関わる証明書を請求した場合や遺言書の閲覧をした場合は、他の相続人らに遺言書が保管されていることが通知されます。
遺留分制度の見直し
まず「遺留分」についてご説明します。
遺留分とは、一定範囲の相続人に対して最低限保証された遺産をもらう権利のことを言います。
例えば相続人が兄弟2人で、父である被相続人が遺言書で「財産はすべて長男に相続させる」としていた場合に、遺留分の制度が無ければ財産は全て長男に相続させることになります。
遺留分の制度を利用することによって、弟は民法で定められた遺留分の割合までの金額を長男に対して請求することができるのです。この請求をする権利を「遺留分減殺請求」と言います。
例えば相続人が配偶者(妻)と子供2人だった場合、総体的遺留分は1/2で、その中で配偶者に1/2、子供たちにそれぞれ1/4ずつ遺留分があります。遺産額が4,000万円だったとしたら総体的遺留分は2,000万円、配偶者はそのうち1/2の1,000万円、子供たちはそのうち1/4ずつの500万円ずつ遺留分があるということになります。
ではこのケースで被相続人が遺言書によって「妻に不動産(遺産額3,500万円)を、子供たちには残りの500万円を半分ずつ相続させる」と記載していた場合どうでしょうか。子供たちはそれぞれ250万円しか相続することができず、遺留分を侵害されていることになります。
ここで今まで問題だったのが、遺留分は目的物の返済請求権という性質だったことです。
子供たちが遺留分減殺請求を行った場合、妻が相続した不動産に対して行われることになりますので、不動産が共有状態になります。
不動産は共有人全員の合意が無ければ売却や処分をすることができなくなります。
このように遺留分減殺請求を行うことによって目的物が共有状態になり処分を行えないことが問題となっていたのです。
この問題を解決するため、2019年7月1日に施行された法改正によって、遺留分減殺請求が目的物の返済請求権から「遺留分減殺請求に該当する金額の支払い請求権」となったのです。名称も遺留分減殺請求から「遺留分侵害額請求」へと変わりました。先ほどの例だと、妻は子供たちに対して現金で遺留分の支払いをすることになります。
これによって遺産を共有状態にすることを避けることができるようになったのです。
ただし、例外なく現金での支払いをしなければならなくなったため、遺留分侵害額請求をされた者は裁判所に請求をすれば支払いを猶予してもらうことができます。
もう一つ、遺留分について改正されたのは遺留分の算定方法です。
改正前の相続法では特別受益については何十年前までも遡って遺留分の算定に含ませることになっていましたが、改正後は「相続開始前10年間にされたものに限り遺留分の対象財産とする」ことになりました。
期間を限定することによって遺留分額が予測できるため、遺留分トラブルの早期解決ができるようになったのです。
相続の効力等の見直し
これまで不動産の相続で被相続人が遺言によって「不動産を全て長男に相続させる」など、法定相続分と異なるとしていた場合、登記をしていなくても自分の権利を第三者に主張(=対抗)することができていました。
これが法改正後は遺言があったとしても登記がなされていない場合は自分の権利を第三者に主張することができなくなりました。
その理由としては「相続債権者」の利益を保護するためです。
例えば遺産が不動産(1,000万円)で、相続人は兄弟2人。被相続人が「兄に全て相続させる」という遺言を残していたが、弟に500万円の借金があった…というケースです。
弟にお金を貸している債権者は、相続開始後に法定相続分を差し押さえて債務を回収する予定でしたので兄より先に登記を済ませていたとしても遺言があれば遺言の内容が優先されていましたので、せっかく登記をしていた債権者が権利を主張することはできなかったのです。
また登記をしなくても相続をすることができるため所有者がわからない状態の不動産が増えていることなども問題視されており、登記制度の信頼が低下していました。
これらの問題を解決するために相続の効力等の見直しが行われたということです。
改正後、相続債権者は各相続人に対して法定相続分に応じた請求をすることができるようになりました。
遺言などによって相続分が指定されている場合は、相続債権者がそれを承認すれば法定相続分に応じていなくても良いとされています。
相続人以外の者の貢献を考慮
「寄与分」といって、被相続人の介護などを行っていた相続人は他の相続人と同じように法定相続分で相続をした場合に不公平であることから、貢献度に応じて遺産を多くもらうことによって不公平を是正する制度です。
例えば遺産が3,000万円で相続人が配偶者(妻)と兄弟2人だった場合、法定相続分で相続をすると妻1,500万円、子供たちは750万円ずつを相続することになります。
これが、兄が長年介護をしていたことに対して相続人全員が遺産分割協議によって寄与分を500万円認めた場合は、相続額は3,000万円-500万円で計算され、妻1,250万円、弟625万円、兄1,125万円となります。
さてこの寄与分ですが、これまでは相続人にしか認められませんでした。
被相続人の介護をしていたのが例えば兄の「お嫁さん」だった場合は相続人ではないので、どれだけ頑張って被相続人の介護をしても遺産を受け取ることはできませんでした。
法改正によって2019年7月1日から「特別寄与料」が認められることになりましたので、相続人以外の親族が無償で療養看護などを行い被相続人の財産を維持または増加させた場合は相続人に対して金銭の支払いを請求することができるようになりました。
まとめ
法改正によって被相続人が亡くなった後の配偶者の生活が苦しくならないように、被相続人が亡くなった後の支払いに困らないように、被相続人の遺言が有効になるように…など、これまでの相続の問題点が大きく改善された法改正ではないかと思います。
使用してみたいけどわかりにくい制度や、裁判所に申し立てる必要のある制度を利用したい場合は法律の専門家である弁護士などに相談してみましょう!