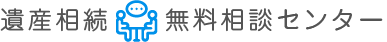| ※こちらの記事の内容は法改正により一部変更された内容が記載されている点があります。 修正された内容はコチラ「相続法の改正で、変更されたポイント」をご覧ください。 |
先日,97歳で死去した資産家の女性が「遺産は全て家政婦に渡す」旨の遺言書を残していたことで,50年以上その女性に仕えてきた家政婦と,実の娘2人が争った裁判の判決が注目されました。
これは,平成23年に死去した97歳の資産家女性が「遺産は全て家政婦に渡す」という内容の遺言を遺していたものの,実の娘2人が遺産を不当に持ち去ったとして,家政婦の女性が遺産の返還を実娘側に求めた裁判でした。
裁判の中で,実娘側は「遺言は母親を騙して作成させたもので無効だ」などと主張していたようです。ところが,裁判所は「資産家女性の立場からすれば,今後を委ねることのできない実娘よりも,たとえ家政婦であったとしても,50年以上にわたり資産家女性に献身的に仕えてきた家政婦に対し,自己の財産を全て譲るという心境になったとしても,人の心情として何ら不自然なことはない」と判断して,家政婦の女性の全面勝訴として,実娘側に宝石類や約3千万円など全遺産の返還を命じた,という事案でした。
上記のとおり,争点の一つに遺言の有効性がありました。
娘側の主張としては「遺言は高齢で判断力が衰えていた母が,家政婦に洗脳され作成されたものであり,そもそも実娘を差し置いて家政婦に遺産を渡そうとするはずがなく,遺言は無効である」というものでした。そこで,今回は遺言と,遺言を作成するための遺言能力について,少しお伝えしたいと思います。
1 遺言とは
そもそも遺言とは,自分が生前に築いた財産について,その処分方法などを言い残しておく,最期の意思表示になるものです。
遺言は満15歳になれば,たとえ未成年であってもすることができます(民法第961条)。
また,民法第960条では「遺言は,この法律に定める方式に従わなければ,することができない」と定めており,遺言が遺言者の真意に基づくものであることを確かなものにするために,民法第967条以下で厳格な方式を定めており,この方式や手続きに従ったものでないと認められないのです。
2 遺言の種類
遺言は大きく分けると,「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります(他に「秘密証書遺言」や「危急時遺言」などの方式がありますが,ここでは省略させていただきます)。
自筆証書遺言とは,遺言者が,紙に自ら遺言内容の全文を書き,且つ,日付と氏名を書いて,署名の下に押印して作成する遺言書です。これは全て自筆で書く必要があり,パソコンやタイプライターなどによるものは無効とされてしまいます。また,加筆訂正,その他の変更についても,遺言者がその場所を指示し,これを変更した旨を付記して特にこれに署名し,且つ,その変更の場所に押印をしなければ,その効力を生じない,と記載方法については厳格に規定されているのです。
公正証書遺言とは,証人2人以上の立ち会いのもと,遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し,それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめます。その後,これを遺言者と証人に読み聞かせ,または閲覧させ,これを承認したら,遺言者と証人がそれぞれ署名押印し,最後に公証人が署名押印して作成します。
自筆証書遺言は,自分で書けばよいので,費用もかからず,いつでも書けるという点でメリットがありますが,一方で,全文自書しなければならないので,病気等で手が不自由になり,字が書けなくなってしまった方は利用することができませんし,遺言者の死後,家庭裁判所で相続人らが立ち会って行う検認手続が必要です。
公正証書遺言は,書名等ができなくなってしまった場合でも,公証人が遺言者の署名を代書することが法律で認められている上,公証役場に出向くことが困難な場合でも,公証人が,遺言者の自宅や病院等へ出張し,遺言書を作成することもできますが,手数料などがかかってしまいます。
3 遺言執行者
相続が発生し,遺言書があった場合,預貯金の解約や有価証券の名義書替,不動産の所有権移転登記,その他資産の売却や貸付金の回収,など遺言の内容を実現するためには実に多くの手続きを行う必要があります。
遺言執行者とは,遺言の内容を実現するために,それらに必要な行為や手続きを行う者のことを言います。
遺言により遺言執行者が選任されている場合,遺言執行者は,相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。この場合,各相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができません。たとえば,相続人やそれ以外の者が相続財産を勝手に売却した場合は,その売却行為は無効となるのです。
遺言執行者を選任しなくても,遺言内容を実行できないわけではありません。しかしながら,争いの発生を未然に防ぎ,遺言の内容を確実に実現するためにも,遺言書を作成する際には,遺言執行者を選任しておく方がよいでしょう。
また,遺言にて子どもの認知,推定相続人の廃除や廃除の取り消しを行う場合などにも,必ず遺言執行者を選任する必要があることに注意が必要です。
4 遺言能力
今回の裁判では,遺言書の有効性について争われました。
法律上有効な遺言をするためには,民法では以下のとおり定めています。
➀ 15歳に達した者は,遺言をすることができる(民法第961条)
➁ 遺言者は,遺言するときにおいてその能力を有しなければならない(民法第963条)
この2つの条件を,いずれも満たさなければなりません。いずれか一つでも欠けている状態で作成された遺言書は無効になってしまいます。
➁については,法律上「意思能力」といい,自分の遺言が法律的にどのような効果を生じるのかを理解できる能力のことをいいますが,高齢の方が遺言を作成しようとするときには特に注意が必要です。
認知症や精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々を保護し,支援する制度として成年後見制度があります。その判断能力の程度など本人の事情によって,後見・補佐・補助の3段階の制度を選べるようになっていますが,この成年後見の制度においては,家庭裁判所によって選任された成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり,本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって,本人を保護・支援するのです。
したがって,成年後見制度の趣旨から考えれば,遺言についても成年後見人等の代理や同意等が必要となるように思われますが,遺言については遺言者の最期の意志を尊重するための制度なので,これらの規定の適用はなく,遺言者本人に意思能力があるかどうかが問題となるのです。ただし,遺言者が成年被後見人である場合,事理を弁識する能力が一時回復したときにおいて遺言をするときには,医師二人以上の立会いがなければならない,と定められています(民法第973条)。
遺言ができる意思能力があるかどうかは,遺言するときにおける遺言者の具体的な状態に応じて判断することになります。よって,認知症であるからといって必ず意思能力が認められないというわけではありません。遺言者が認知症であったとしても,その程度や理解力,遺言を作成しようとした動機や,その遺言によって生じる法律効果の複雑性などを総合的に判断して,遺言者がその内容や効果を理解できるような場合には,その遺言の作成について意思能力があったと認められるのです。
公正証書遺言であっても,遺言能力が否定されて遺言が無効となった例はあります。公証人は医学の専門家ではないので,遺言者の遺言能力についての正確な判断はできません。公証人の面前での受け答えに不自然な点がなければ,実務上は公正証書遺言が作成されてしまうでしょう。
相続開始後の争いを回避するためにも,遺言作成時に,遺言者に認知症など判断能力の低下が疑われるような場合には,弁護士などの専門家に相談のうえ,場合によっては医師の診断を受けたうえで,判断能力の有無をきちんと確認するなどして,慎重に遺言書を作成することをお勧めします。当センターでも相続のご相談は承っております。ご相談は無料ですので,お気軽にご相談下さい。